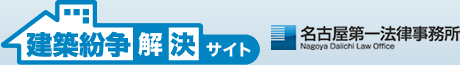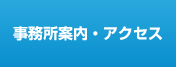「根太レス工法」を考える-その2
「根太レス工法」で建てる場合の注意、建ててしまった場合の対策
弁護士 田原裕之
前回に続いて、「根太レス工法」についての記事です。
「根太レス工法」で建てる場合の注意
設計図を見ましょう。特に「矩計図」(「かなばかりず」と読みます。建物の断面を書いた図面で、基礎から屋根までの構造、仕様が書かれています。下の図がサンプルです。


上の図を見ると、「大引き」の上に「根太」がないことがわかります(言葉の意味は前回記事をご参照ください)。「根太レス工法」です。
これを根太工法に変えようとすると、「根太の高さ45㎜」-「構造用合板を24㎜から12㎜に薄くする差12㎜」=33㎜、床の高さが高くなります。建物全体の設計変更につながり、変更は一大作業です。工事費用も高くなってきます。特に、ハウスメーカーの場合、根太レス工法を根太工法に変えてくれといっても、なかなか認めてもらえないでしょう。
そこで、「根太レス工法」を取ることにしたとします。
対応策1
一つ目は、構造用合板の厚さを厚くすることです。24㎜を28㎜にするだけでも、違います。
根太レス工法が用いられ始めた当初、24㎜を使う例が多かったのですが、施主からのクレームが多かったためか、28㎜を採用する例が増えてきています。
前回記事で紹介しました建売住宅でも、28㎜の構造用合板が使用されていました。
この変更であれば、差し引き4㎜の増加ですから、設計変更はそれほど大きなものにはなりませんし、費用増加も少なくてすみます。
対応策2
もう一つの方法は、大引きの間に「受け材」を455㎜間隔で置くことです。
前回の感覚的計算をしますと、従来の「303ミリ間隔根太+12㎜構造用合板」よりも「455ミリ間隔大引き・受け材+24㎜構造用合板」が同等以上となりますね(正確な計算ではありません)。
「受け材」は大引きの上に配置せず同じ高さで設置しますから、床の高さは変わりません。
ある建築士の方は、「たわみなどが怖いから受け材を用いる設計をしている」と言われていました。
この場合も、費用は高くなります。「910㎜間隔大引き+24㎜構造用合板」でも構造上は問題ありません(但し、床に重い家具などを置いた場合、長期的に大丈夫なのか、という個人的疑問はあります)。構造上大丈夫なのだから、費用をかけることを回避するか、費用をかけてでも「たわみ」「踏み心地の違い」を回避するか、そこは施主の方の決断です。
「根太レス工法」で建てた場合
「根太レス工法」で建ててしまって、竣工後、床の「たわみ」「踏み心地の違い」がどうしても気になる場合。
構造用合板の厚さを厚くすることは不可能です。
これに対して、「大引きの間に455㎜間隔に受け材を設置する」ことは可能である、と建築士の方から伺いました。そして、その受け材を「床束」で支えるのです。一方、床下から作業することは実際には不可能で、床を捲らなければ工事できないという建築士の方もいました。
前回の記事の最後で触れましたが、「根太レス工法が瑕疵だ」と言えれば、その費用は施工業者、設計をした建築士に請求することができますが、「瑕疵とは言えない」ことを前提にすると、その費用は、施主が負担することにならざるを得ないでしょう。ここでも、「たわみ」「踏み心地の違い」を我慢するか、費用をかけてでも解消させるかの決断です。