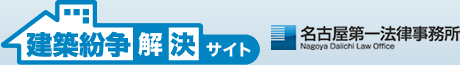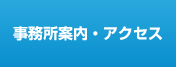建築士片山先生の「住宅の構造を学ぶ」の講義を受けて
 最初に熊本地震ではどうしてあんなに建物が壊れたのか、というお話を伺いました。
最初に熊本地震ではどうしてあんなに建物が壊れたのか、というお話を伺いました。
1981年、建築基準法改正で「新耐震基準」が施行されましたが、新耐震基準は、震度6強程度の地震で、その建物が相当の損傷は受けるが、倒壊はしないというものです。建物の内で人が死亡しなければいいという基準ということです。
そして、大きな地震が起こるたびに法改正が行われているということです。倒壊を防ぐための壁の配置バランスや土台と柱の緊結方法は2000年に初めて基準が設けられ、この導入は阪神・淡路大震災がきっかけとなったということです。
また、最近は、2階と1階の壁がずれているという「間くずれ」の平面が目立つということでした。木造2階建ての住宅では構造計算が不要で「壁量」とバランスの基準しかないため、「間くずれ」は規制されていないそうです。これを聞いて、まだまだ耐震性に関しての法改正は万全ではないんだということが分かりました。
私が事務担当させて頂いている建築紛争の案件が、まさにこの「間くずれ」によるものでしたので、興味深くお話しを伺えました。
主に構造と基礎のついての講義をして頂きましたが、一番興味のあったお話は、「浮き基礎(コロンブス工法)」についてでした。これは建物の重さと同量の地盤(砂)を捨てて、その部分に発砲スチロールを敷き詰めるという地盤改良工法。つまり、海に浮かんでいる船と同じ感覚で建物が建っていると考える工法です。発砲スチロールに上に建物が建っている状況を考えると建物の重さで凹んでしまうのではないか、脆くすぐに崩れてしまうのではないかと考えがちですが、発砲スチロールは丈夫な素材であり、液状化にも強く、高速道路の土盛りなどの土木工事でも使用されている工法であるということを知りました。
 地層について知りたい場合には、「地質調査図」を取得すれば判ることや、溶接作業は雨・風に弱いので、基本的には工場で行われること等、興味深いお話しを沢山聞けて、学ぶことが多かったです。
地層について知りたい場合には、「地質調査図」を取得すれば判ることや、溶接作業は雨・風に弱いので、基本的には工場で行われること等、興味深いお話しを沢山聞けて、学ぶことが多かったです。
建築の用語は難しいため、講義中もわからないものがありましたが、片山先生のレジュメ内で写真入りで説明して頂いているものが多かったため、とても分かりやすく勉強になりました。
現場で実際に自分の目で確かめてみることが、建築の構造や基礎の勉強につながるのではないかな、とも思いました。
まずは、少しでも建築用語に慣れ、弁護士の仕事にお役に立てるようになりたいと、改めて思いました。
(執筆:建築法務部 事務局)