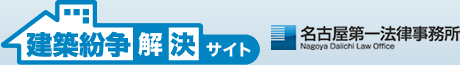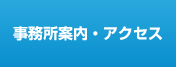長年住んだ家に瑕疵が見つかった場合 ~「居住利益」分の賠償額~
家を建ててしばらく経ってから瑕疵が見つかり,建築業者に対して損害賠償を請求すると,業者側から「【その建物住んできたこと】を利益として考えて,損害賠償額から控除すべきだ」と主張されることがあります。
 この【建物に住んできた】という利益を「居住利益」といいます。他人の家を借りるときには家賃が発生するように,「住む利益」を金銭的に評価したものです。
この【建物に住んできた】という利益を「居住利益」といいます。他人の家を借りるときには家賃が発生するように,「住む利益」を金銭的に評価したものです。
「損害額から居住利益を控除すべき」という主張の根拠としては,「賠償金が全額認められれば,施主はあらためて新築建物を取得できることになって不当だ」という考え方が背景にあるようです。
しかし,この考え方には次のような問題があるとして批判されていました。
① 倒壊等の危険にさらされながら瑕疵のある建物をやむなく使用していることを「利益」とみることはできない(危険な欠陥住宅を他人に貸して賃料収入を得ることなどできない=利益を生まない)。
② 本来であれば,完成引渡時から瑕疵のない建物を使用できたのに,長年にわたって欠陥住宅に住むことを強いられてきたのはむしろ「継続的な不利益」である。
③ 業者側が争うことで長引けば長引くほど,居住期間が増えて居住利益も膨らんでいくため,受けられるべき賠償額が減っていくことになり,手抜き工事をし,かつ交渉に不誠実な業者ほど好都合な結果を招くことになる。
このような居住利益を控除すべきかどうかという論点について,最高裁判所は,「新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物全体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるとき」には,居住利益を控除できないと判断しています(最高裁平成22年6月17日第一小法廷判決)。
 この判例は,新築建物の売買の事例ですが,建築工事を依頼して完成引渡を受けた新築建物が欠陥住宅であった場合にも同様にあてはまります。
この判例は,新築建物の売買の事例ですが,建築工事を依頼して完成引渡を受けた新築建物が欠陥住宅であった場合にも同様にあてはまります。
この判決は,「新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合」すなわち建て替え費用相当額の損害賠償請求が認められる場合であって,なおかつ,「建物全体が社会経済的な価値を有しないと評価すべき」ときに,居住利益の控除を否定したものですので,瑕疵の程度によっては,建て替え費用相当額から居住利益の控除が認められる余地は残っています。
とはいえ,建て替え費用相当額の損害賠償請求をする場合,「構造耐力上の安全性に欠け,建物が倒壊する具体的な恐れがある」ことは多いですので,もしも業者側から居住利益分を引くと言われたら積極的に活用したい判例としてご紹介させていただきます。