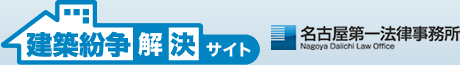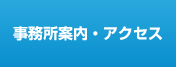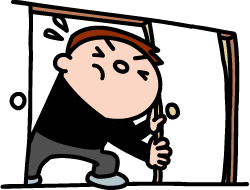依頼者の方は、長屋の1軒で飲食店を営んでいましたが、隣が空いたので、その1軒分を購入し、店舗を拡張することにしました。ところが、その施工がずさんであるために代金の支払を保留していました。それで、施工業者から工事代金を請求する訴訟を申し立てられたのです。
依頼者の方は、長屋の1軒で飲食店を営んでいましたが、隣が空いたので、その1軒分を購入し、店舗を拡張することにしました。ところが、その施工がずさんであるために代金の支払を保留していました。それで、施工業者から工事代金を請求する訴訟を申し立てられたのです。
現地を見分してびっくりしたのは、元の部分と買い増しした部分の間の柱、壁が全部取り壊されていたことです。長屋の場合、柱や筋違で建物強度を確保してありますので、それを撤去すると建物強度が著しく低下します。その補強として鉄骨が組まれていたのですが、その組み方も基礎への接合も問題がありました。構造専門の建築士にも調査してもらいましたが、建物強度を回復するには相当な費用が必要でした。
施工不備にとどまらない、構造上の欠陥があったのです。 裁判では、この点を主張し、修補費用を控除した残金を支払うことで解決しました。
リフォーム工事では、建築確認が取られなかったり、建築士が設計しないことが多く、構造上の問題がある場合が少なくありません。 リフォームでも、建築士に依頼してきちんとした設計をしてもらうことが大切です。
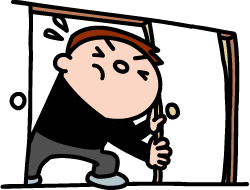 Aさんは、地代不払いで、建物収去・土地明け渡し請求訴訟を起こされました。この建物は3年前に建てたばかりのAさんのマイホーム。Aさんは、すでに半年以上地代を支払っていませんでした。
Aさんは、地代不払いで、建物収去・土地明け渡し請求訴訟を起こされました。この建物は3年前に建てたばかりのAさんのマイホーム。Aさんは、すでに半年以上地代を支払っていませんでした。
「なぜ地代を支払わなかったの?」。聞いてみると、地主イコールAさんのマイホームを建てた建築業者で、もともとの契約が、建築業者の所有する土地上に借地権を設定し、Aさんがその建築業者に建物建築を依頼するという形の建物建築請負契約でした。建物は住宅ローンを組んで建てたので、建物の建築代金は、すでに住宅ローン会社から直接建築業者に全額支払われていました。ところが、新築のマイホームの居間のふすまが入居後1年くらいから開きにくく、2階のドアも開きにくい、窓に隙間が生じそれが拡大しつつある…。Aさんは建築業者さんに連絡をし、修繕を依頼しました。建築業者が差し向けた大工さんがふすまやドアを調整しましたが、その後ほどなく開きにくくなったため、また修繕を依頼しましたが、今度は来てくれませんでした。Aさんは自分で考えて、地代の支払いを留保することで、修繕を促そうとしたのです。
「被告」という形で裁判が始まったため、まずは、ふすまやドアの擦れた跡や、窓の隙間の写真を裁判所に提出しました。それを見た裁判官が「地盤が沈下してやしないか…。」とつぶやきました。
恥ずかしながら、代理人はそれまで地盤沈下は全く考慮していませんでしたが、裁判官のこの一言で、建築士さんに測ってもらったところ、Aさん宅の1階の居間と、2階の居間の真上の部屋を中心に、数センチ南側が低くなっていました。そのために、調整してもドアやふすまが開きにくくなっていたのです。
裁判の中で、検証が行われ、スウェーデン式サウンディング試験※をやったところ、「自沈」。地盤沈下の原因は、建築業者が土地にL字鋼を埋め込むために土地を掘削したあとの突き固め不足と、土砂の流出と推定されました。
Aさんには、地盤改良費用と、自宅の修繕費用の損害賠償が認められました。もちろん、建物収去・土地明渡はみとめられませんでした。
Aさん自身も、地盤沈下には気づいておらず、裁判を起こされたために損害に気付いたというケースでした。
※スウェーデン式サウンディング試験・・・地盤強度を調べる方法
 依頼者の方は、賃貸用の3階建てのアパートを新築しましたが、注文したとおりの仕様でないところが多く、訴訟をしたところ、1審で敗訴してしまいました。
依頼者の方は、賃貸用の3階建てのアパートを新築しましたが、注文したとおりの仕様でないところが多く、訴訟をしたところ、1審で敗訴してしまいました。
控訴審からご依頼を受けたのですが、建築士さんにみてもらったところ、建物が設計通りに施工されておらず、擁壁や建物基礎に関して、構造耐力上、安全性に問題があることがわかりました。また、鉄骨や梁は、断熱性のある材料で覆わなければならないと法律で定められているのですが、それがなされていない部分も散見されました。安全性に大変な問題があったのです。その他にも、いくつかの法律違反が認められました。そこで、これら安全性や法律上の欠陥にしぼって訴訟でその修理費用等を請求しました。
控訴審の裁判ではこれらの欠陥があることが認められ、修理するための費用、修理期間中の賃料相当損害金、引っ越し費用相当損害金、調査費用、弁護士費用等を支払えとの判決を得ることができました。
設計図通りの施行がなされているか、構造上安全性に問題がないかは、消費者にはわかりにくいことが多く、専門家の助力を得て、はじめて問題があることがわかる場合もあります。安全性に問題が有ることに気がつかないでいると、人命につながる損害が生じかねません。修理ができてほんとうによかったとおもいます。
建設予定地は、ひな壇のようになっており、下の道路から4メートルほど上に建築予定地、そこから4メートルほどの擁壁の上に土地があるという形状でした。
敷地からは眺望が開け、依頼者の方は、広いテラスを設置して、そこにイスを置いてよい景色を眺めることを楽しみにしていました。
ところが、出来上がった建物のテラスは1メートルほどしかなくなっていました。 何故そんなことが?
通常、擁壁は上の土地の所有者が築造するのが普通で、擁壁の底板は上の土地側にあるのです(「L型擁壁」といいます)。ですから、擁壁の下側が境界になります。ところがこの土地の擁壁は建設予定地の元所有者が築造したもので境界は擁壁の上でした。この場合、擁壁の底板は下の土地にありました(「逆L型擁壁」といいます)。
この場合、底板の上に基礎を建てることができませんから、基礎を擁壁から離れたところに築造し、そのために建物全体の配置がずれてしまったのです。そのしわ寄せがテラスに及び、テラスが狭くなってしまったのです。
依頼者の方は、基礎を組んでいる途中で位置が違うことに気づき、是正を求めたのですが、建築が進んでしまい、途中で工事を中止させたときには、建物がほとんど出来上がった状態になっていました。
この件では、途中解約による出来高精算をしたのですが、建物位置のズレを相当考慮して解決することになりました。
推測するところ、この建物の設計をした建築士は、現場確認しなかったと思われます。そのため、擁壁が通常のL型擁壁であると思い込んで、建物位置を決定したのでしょう。現地確認して、逆L型擁壁であることを認識していれば、それに添った設計をしたはずです。
施主が設計段階でこのような問題に気づくことはほとんど不可能です。建築士の責任は重大です。

 依頼者が居住している建物は古くからあるもので、依頼者やその先代が必要に応じて増改築をしてきたものでした。この建物に傾き、ひび割れ、排水異常が生じたのは、隣地工事が原因でした。その当時、隣地ではマンション建設のため、地面の掘り下げが行われていました。そして、地面を掘り下げる際、通常であればしっかりと土留めを行うのですが、マンション建設業者の行った土留めが一部崩れ、それに併せて依頼者宅を支える地面の一部が沈下し、上記の不具合が生じたのです。
依頼者が居住している建物は古くからあるもので、依頼者やその先代が必要に応じて増改築をしてきたものでした。この建物に傾き、ひび割れ、排水異常が生じたのは、隣地工事が原因でした。その当時、隣地ではマンション建設のため、地面の掘り下げが行われていました。そして、地面を掘り下げる際、通常であればしっかりと土留めを行うのですが、マンション建設業者の行った土留めが一部崩れ、それに併せて依頼者宅を支える地面の一部が沈下し、上記の不具合が生じたのです。
さて、このケースでは、責任の所在も問題になりましたが、とくに問題になったのは、損害をどのように算定するかでした。
まず、通常のケースでは修補見積もりを取得して、それが損害額の基準となるのですが、このケースでは建物が非常に古かったために固定資産税の評価上は大変低額な建物でした。そのため、修補見積額が建物の固定資産税の評価額を大きく上回ってしまいました。マンション建設業者側は、全損でも固定資産税の評価額を基準とすべきことから、一部損壊で補修する場合に全損の場合以上の賠償の必要はないと主張しました。当方としては、そのような低額の賠償では到底、建物を補修できない、固定資産税の評価額が必ずしも客観的価額を反映しているわけではない、と反論しました。
次に、この建物が古かったゆえに、修補見積もりどおりに修補してしまうと建物が従来よりも強化されてしまうという問題もありました。理論的には事故直前と比較して痛んだ部分が損害なので、修補見積もりは事故直前と同様に修理するものであるべきです。しかし、建物が古かったため事故直前と同様に修理するのは不可能で、修理をすればどうしても事故直前よりも強化されてしまうのです。このように強化されてしまう部分については損害との関係でどのように理解すれば良いのか悩みました。
そして、このケースでは、依頼者が裁判による解決を望みませんでしたので、裁判所の判断が示されることなく、マンション建設業者と訴訟前に和解をしましたが、上記の2つの問題について、みなさんは、どう思われますか。
 依頼者の方は、長屋の1軒で飲食店を営んでいましたが、隣が空いたので、その1軒分を購入し、店舗を拡張することにしました。ところが、その施工がずさんであるために代金の支払を保留していました。それで、施工業者から工事代金を請求する訴訟を申し立てられたのです。
依頼者の方は、長屋の1軒で飲食店を営んでいましたが、隣が空いたので、その1軒分を購入し、店舗を拡張することにしました。ところが、その施工がずさんであるために代金の支払を保留していました。それで、施工業者から工事代金を請求する訴訟を申し立てられたのです。