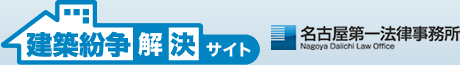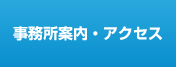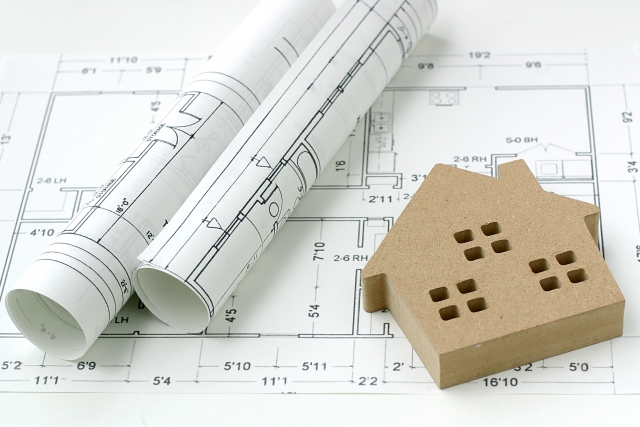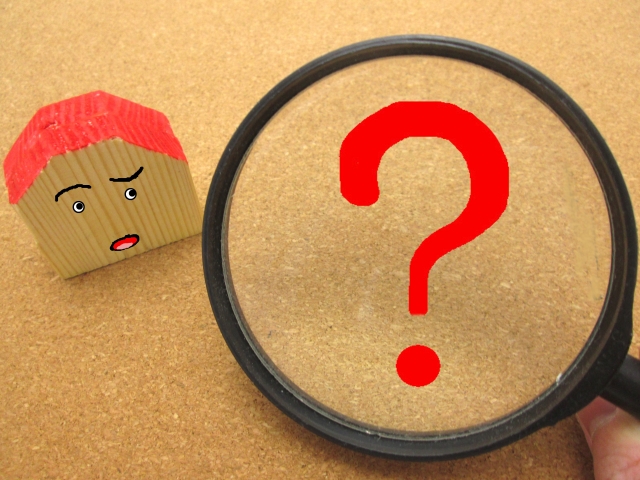2023年10月20日、構造設計を手がけていらっしゃる浅井洋樹建築士をお招きし、「4号特例って何?」というテーマで所内勉強会を開催しました。

建築基準法6条1項4号に定義される建築物(一般的な木造二階建の戸建て住宅はこの「4号」建物にあたります)は、構造や設備などの一部の規定の審査が免除されるという特例があり、「4号特例」と言われています。ところが、この4号特例に関して法改正がされ、2025年に施行されることになっています。そこで、今後どう変わっていくのかなど具体例とともにとてもわかりやすく教えていただきました。
法改正に関しては、建築業界団体からは負担が多くなることから反対の声があがっていますが、消費者にとっては審査の免除が欠陥住宅の温床になっていることを考えれば、4号特例はなくしていくべき制度であるものの、国土交通省が実際にどのように運用していくのかということが重要であるとのご指摘がありました。
勉強会の後、11月1日に国土交通省が2階建て木造戸建て住宅などの確認申請・審査マニュアルを公表し、構造審査で求められる図面の添付を省略する代わりに「仕様表」などの提出を求めると発表しました。果たしてこの運用によって、建物の安全確保を図ることを実現できるのか、引き続き注目していく必要がありそうです。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家特措法」)が一部改正されました。この改正で「固定資産税が6倍になる」とまことしやかに言われています。正確なところを説明します。なお、今回の法改正では所有者不明の場合の管理制度など他の部分の改正もなされましたが、ここでは、「固定資産税6倍化」に絞って説明します。

■ 「固定資産税が6倍」の意味とは? ■
土地には固定資産税がかかります。その土地の上に家屋が建っている場合には、特例が適用され最大6分の1に減額されます。家屋がなくなると減額されず標準どおりの固定資産税が課せられます。これが「6倍化」の意味で、 6分の1減額の特例適用がなくなるため、結果として土地(敷地)の固定資産税が6倍になる ということです(建物の固定資産税ではありません)。これは、今回の空家特措法改正によっても変わりません。
■ どこが変わったの? ■
これまでの空家特措法では、「特定危険空家」(その意味の説明は省略)と認定され、改善などの勧告がなされると、特例除外=6倍化される仕組みでした。
今回の改正法で、「管理不全空家」という概念が追加されました。この「管理不全空家」というのは、「放置すれば特定危険空家になってしまうおそれがある空家」、という意味です。特定危険空家の前段階と言えるでしょう。市町村によって、「管理不全空家」と認定され、管理などの勧告がなされると、特例除外=6倍化される、という仕組みが今回の法改正で導入されたのです。特例除外の要件が、 「特定危険空家認定+改善勧告」が「管理不全空家認定+管理勧告」に早められた と考えていただければ結構です。
この説明でもおわかりのように、管理不全空家に認定されることで自動的に土地の固定資産税が6倍になるわけではありません。対象家屋所有者には管理勧告が届きます。この勧告が届くと土地の固定資産税が6倍になることになります。
この改正は、 令和5年12月13日 から施行されています。所有している家屋が空家の方、要注意です。

■ 注意 ■
最後に、「だったら、管理勧告が来るまでほおっておけばいい、」というのは誤りです。管理不全空家は放置すれば特定危険空家になってしまうという意味ですから、既に草が伸び放題、落ち葉が隣の庭に落ちる、屋根瓦が落ちて(台風で飛んで)通行人にケガをさせる(隣家のガラスを割る)など近所迷惑が起きているはず。管理不全空家に認定されたら、いや、認定される前に家屋の管理には万全の注意を払いましょう。
基礎の構造決定方法について、纐纈 誠一級建築士をお招きし、勉強会を開催しました。
建築物は、建物自体の重さや、家屋内にある家財等の重さ、地震等の振動や衝撃等に対して、安全な構造を持つ必要があります(建築基準法20条)。建物の基礎は、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければなりません(建築基準法施行令38条1項)。そこで建築基準法施行令38条1項、同3項、国交省告示1347号第1第1項は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度に応じた基礎(20kN/㎡未満の場合は基礎ぐいも用いた構造等)を定めています。
この「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力」は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければなりません(建築基準法施行令93条)
地盤調査結果を受けて、地盤の許容応力度を定める方法は、国土交通省告示1113号第2で定められていますが、同法が、地震時に液状化の恐れのある地盤や、基礎の底部より下2m未満までの間にスウエーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合等には、同条が示す計算式が本来使えず、構造計算によらなければならないとされているにもかかわらず、同計算式を使ってしまう問題のあるケースがあるとのことです。これらの地盤では、ほんらい、地盤改良や、柱状改良、又は杭基礎などの地盤補強工事等の対策をとる必要があるにもかかわらず、これがなされておらず、床面や基礎天端に施工誤差ではあり得ないような不陸が生じたり、不同沈下などの問題が生じているケースがあるとのことでした。
地盤調査の方法や、調査結果の読み方、地盤補強工事のするその特性、長短所、建築後に地盤改良不足が発覚した場合の事後的な補強方法など学ぶことができ、大変有意義な勉強会でした。

土地Aと土地Bが隣地同士であり、土地Bには従前から建物が建っていました。土地Aを購入した注文者は、工事業者に対して土地A上に自宅の建築を依頼しました。当該工事業者は、土地Aと土地Bとの間にブロック塀を建てるため、土地Bとの境界に近い土地Aを境界に沿って25cm程度掘り下げました。その後、土地B側に土地Aとの境界に沿って設置されていたコンクリートブロック擁壁より深い部分の地盤の土が崩れ、土地の犬走り部分にヒビ割れが生じ、同じ部分に設置されていた温水器が倒れ、当該擁壁に設置されていた温水器(屋根に設置されたソーラーパネルで集熱し、温めた湯をためて置く装置)が倒れ、当該擁壁に設置されたアルミフェンスの一部が損壊したのです。

この時、当該工事業者は、自らが加入する請負賠償責任保険で対応しようとしたところ、地盤崩落免責に該当すると保険会社からいわれ、保険金の支払いを受けることができませんでした。
地盤崩落免責とは、
① 地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した土地の沈下・隆起・移動・振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の滅失、破損または汚損について法律上の損害賠償責 任を負担することによって被る損害
② 地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した地下水の増減について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
について免責とするというものです。
当該工事業者は、自らが賠償責任を負うような場面で保険に加入していたにもかかわらず、思わぬところで保険金が支払われないという場面に遭遇してしまったのです。結局、全額について自身で賠償金を工面して支払わなければならず、こんなはずでは無かったのにという事態が生じてしまいました。こういったことの無いように、これを読まれている工事業者の方は、自身が請負う工事との関係で生じやすい損害がきちんと補填されるようになっているかを改めて確認をしておかれることをお勧めします。
最近の建物は気密性が高くなってきました。そのため、建物の外壁に湿気がたまると、結露の原因となったり、木材の耐久性が損なわれてしまうという問題も生じてきました。
その問題を解決するために考え出されたのが、「(外壁)通気工法」(通気「構法」と書かれることもあります)です。
どんなものかは下の図を見ていただきたいのですが、要するに、建物躯体と外壁の間に空気が通る層を作って、水蒸気を建物外に追い出してしまう工法です。

これにより、結露を防止する、躯体部材の乾燥を保ち建物耐久性を確保するという効果が得られます。
最近の建物(住宅)ではほとんど通気工法が用いられるようになりました。特に、瑕疵担保履行保険付きの住宅では、通気工法とすることが保険の条件とされています。
ここで、注意しなければならないのは次の点です。
1 胴縁
建物躯体に直接外壁材(最近では 窯業系サイディングを用いることが多いです)を貼ることはありません。「胴縁」という木材を打ってそれに外壁材を貼り付けていきます。この胴縁が「通気胴縁」になっているかです。胴縁のところで空気の流れが遮断されてはいけません。建物完成後は、外から確認することができなくなりますので、建築中に確認しておきましょう。
2 外壁の上下
折角外壁が「通気」していても、その上下が塞がっていれば、空気は通りませんね。外壁の一番下には、「水切り」という金属製の部材が入っています。そこから空気が出入りできるようになっていることを確認してください。外壁の一番上は屋根のひさしの下になりますね。この部分が塞がれていることが時々あります。ここから空気が抜けるようになっていますか?
今回は、「通気工法」について説明しました。

Q. 台風による強風で西側の家の瓦が飛ばされてきて、車に傷が付いてしまいました。
瓦の所有者に損害賠償を求めることはできるでしょうか?
A. 一部または、全部の損害賠償が認められる場合もあります。
民法717条1項は、建物などの「土地の工作物」の占有者や所有者は、その設置や保存に「瑕疵」があって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務があると定めています。建物が通常備えるべき安全性に欠けている場合には、「瑕疵」があるとされます。
過去に幾度も台風が来ているような地域においては、一般に予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないよう、屋根瓦を固定するなどする義務があります。
台風が来て、付近一帯の瓦は飛ばされていないのに、燐家の瓦がいくつも飛散しているような場合には、瓦の固定が不十分であったと推認され、賠償が認められる可能性は高いでしょう。
一方、予想される以上の、今までにないような強風が吹いたり、竜巻が起きたような場合、付近一帯の瓦も飛んだような場合には、「通常備えるべき安全性を欠いていた」と認められることは難しく、「不可抗力」とされる可能性が高いといえます。また、どの家の瓦により被害を受けたのか、特定することもなかなか難しいと思われます。
 建築紛争事件が、裁判に持ち込まれると、瑕疵にあたるかどうかの判断と、瑕疵と認められた場合の修補費用が問題になるのが通常です。
建築紛争事件が、裁判に持ち込まれると、瑕疵にあたるかどうかの判断と、瑕疵と認められた場合の修補費用が問題になるのが通常です。
瑕疵にあたるかどうかの判断には、建築の専門知識が不可欠です。修補費用の算定についても同様です。
しかし、裁判官は、法律の専門家であっても建築の専門知識はないため、建築関係訴訟には、イ 調停委員、ロ 専門委員 という制度が用意されています。また、必要に応じて鑑定が行われることもあります。
これらの制度が利用されるのは、通常、争点整理が終わり、瑕疵一覧表が完成した時点になります。調停委員、専門委員、鑑定人となるのは、裁判所が委嘱した一級建築士、構造設計一級建築士等です。建築士の方にもそれぞれ専門があるので、事案に応じてふさわしい人を選任しているようです。
【調停委員】
「付調停」という決定がなされ、調停委員として、参加します(民事調停法20条)。
調停というと、一般民事調停や家事調停を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょうが、当地(名古屋)における建築関係訴訟の場合、裁判官があくまで調停の主催者で、調停委員は、建築の専門家の立場から意見をいうというのが通常です。民事訴訟手続きにおける「(現場)検証」制度は、調停委員が選任されてから、「現地調停」という形で行われます。
調停は話し合いによる解決を目指す制度であり、調停委員は、調停の最終段階で瑕疵にあたるか否か、瑕疵と認めた場合の修補費用についての意見をのべます。鑑定の場合や、私的に建築専門家の意見を聞く場合は、費用負担が問題になりますが、調停委員は、原告・被告からみると、無料で専門的意見を言ってくれるので、すごく助かる制度です。調停委員の意見は口頭の場合もありますが、書面化されている場合の方が多いと思います。調停委員の意見を踏まえて調停が成立することが少なくありません。また、調停が成立せず、尋問等に進む場合も、調停委員の意見は判決に反映されることが多いので、調停委員の意見の内容は重要です。
【専門委員】
専門的な知見に基づく説明を聴くために、専門委員を選任して、訴訟手続きに関与してもらう制度です(民事訴訟法92条の2)。調停委員は、意見をのべますが、専門委員は、意見を言うのではなく、専門的な知見に基づく説明をするにとどまります。
当地(名古屋)の裁判所では、専門委員制度はあまり利用されていませんが、他地域では調停委員ではなく専門委員が活用されているところもあるそうです。
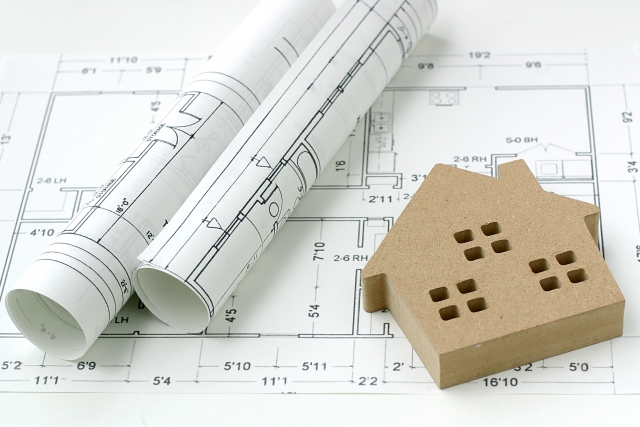 【鑑定】
【鑑定】
通常の建築関係訴訟は、建築士の調停委員がつくので、鑑定の必要性がないことが多いのですが、例えば壁の内側が腐朽しているか否か、どの程度の腐朽であるかなどが瑕疵の重要な内容である場合は、鑑定が必要になることがあります。鑑定人に選出されるのは、やはり一級建築士等の専門家です。鑑定の場合、鑑定費用の予納が必要です。
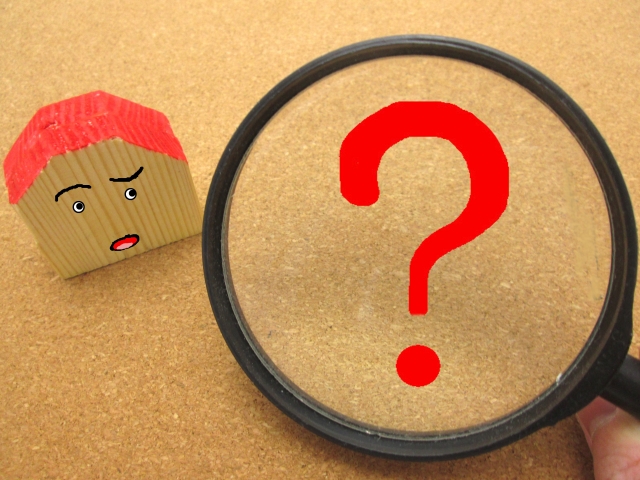
住宅を新築し、瑕疵担保履行保険が付けられています。住宅の基礎に重大な欠陥があるのに、工事業者が補修費用を支払ってくれません。直接保険会社に請求できないのでしょうか。
制度がかなり複雑なので、以下、その概要を説明します。
平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡した建設業者・宅建業者(ご質問は、新築請負ですので、以下、「建設業者」として説明します)は、「保険の加入」または「保証金の供託」をすることが義務づけられました。これは、「住宅品質確保法」に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を確保するためです。
対象となる瑕疵(欠陥)は、「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」についての瑕疵です。
これらの瑕疵のために住宅を建築した方(施主、注文者)が損害を蒙ったときに、建設業者の補修費用などの損害賠償金を保険会社が支払ってくれるという制度です。
原則的には、建設業者が一旦、施主に補修費用などの賠償金を支払い、その後に、建設業者が保険会社から支払を受けるという順序になります。

しかし、建設業者が倒産してしまったというような場合は、建設業者からの補修費用などの賠償金の支払いは見込めません。
そこで、法律では、「建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないとき」には、施主が直接保険会社に請求できると定めています(これを施主の「直接請求」といいます)。
どういう場合に直接請求できるかについて、国土交通省は、「建設業者が破産等により存在しなくなった場合を含め、建築業者による特定住宅建設瑕疵担保責任の履行がなされない場合」と説明しています。
ところが、保険約款や保険会社の実務では、「倒産」「所在不明」の場合に限定されるようになっています。つまり、施工業者が現在も営業している場合には、直接請求を認めない、という扱いです。
施工業者が瑕疵の存在を争って裁判が長期化している、営業はしているが補修費用などを賠償する資力がない、というような場合、「まず施工業者から支払ってもらえ、保険会社は支払わない」というのでは、瑕疵の損害から施主を守る、というこの保険の趣旨が損なわれます。

そこで、日弁連は、「事業者が倒産したとき」に限らず、「発注者等の最初の請求から1年程度が経過している場合」も法律が定める「建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないとき」に該当するとの見解を示しています。
現在、当事務所で、この問題を真正面から取り上げて、保険会社に保険金の支払いを求める訴訟を申し立てています。
最初にも書きましたが、この制度は相当複雑です。瑕疵担保履行保険のことでお困りの方は、当事務所(建築法務部)までご相談ください。
※ 瑕疵担保履行保険の仕組みについては、「住宅瑕疵担保責任保険協会」のサイトをご参照ください。

当事務所建築法務部において4回目となる勉強会を2017年9月22日に開催しました。
今回は、NPO法人「欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」や「住まいのホームドクター/設計者の会」の創立メンバーで、東海地方において欠陥住宅問題の先駆者である滝井幹夫一級建築士に講師をしていただきました。テーマは、「建築士の業務について」でした。
【建築士法の規制】
建築物は、美しさだけではなく、建物としての使用目的・機能が求められ、街並みを構成し、安全性すなわち関係者の生命身体及び財産に損害を与えないことが求められます。
そのため、建築物の技術的水準を確保、質の向上を図るために、一定規模・構造の建築物は建築士でなければ設計・監理ができないと定められているとのご説明がありました。
具体的には、
① 木造建物では、延べ面積100㎡を超え、あるいは、3階建て以上の建物
② 鉄筋コンクリートや鉄骨造などの建物では、延べ面積30㎡を超え、あるいは、3階建て以上の建物
の場合には建築士が設計・監理を行わなくてはならないとされ、安全性の確保が図られています。

【技術の向上と昔ながらの工夫】
設計においては、最近の法律では安全性などを重視するあまり、高気密高断熱など、人工的な環境にするように法律の制定などが進められる傾向にあるが、建築主の生活の仕方に合わせながら、建材選びを工夫するなどして、四季に応じた室内環境にしていくことが必要ではないかと言われていました。た。
【施工者と監理者の分離】
監理においては、工程における重要なポイントを深い経験値に基づいて、立ち会い・目視・計測でのチェックをしていくべきであるが、建築士と施工会社とが平等な関係といえない場合には、どこまで建築士がチェックをして、適正な監理をしていくことができるかは難しいということでした。そのため、滝井建築士が所属されている「欠陥住宅をつくらない住宅設計者の会」においては、請負業者の下請けにならないと申し合わせ、設計監理の契約は建築主と結び、設計監理と施工の分離を徹底されているそうです。
【設計監理契約締結のタイミング】
建物イメージ図や各種図面を作成し、法令チェックなどをした上で、設計監理契約をすることが多いそうですが、その直前で施主の気が変わってしまい困ることもあり、建築士としては契約のタイミングは悩ましいというお話がありました。
【さいごに】
建築紛争においては、建築士の先生方に協力していただきながら進めることが多いですが、今回は、日頃の業務の内容を伺うことができ、また疑問にもお答えいただくことができ、大変有意義な機会となりました。
● 住宅瑕疵担保履行法とは
住宅を新築した(請負契約),新築の建売住宅を購入した(売買契約)後,建物に重大な瑕疵が見つかった。建築業者や販売業者に賠償請求したいと考えていたら,業者が倒産してしまった。賠償請求できなくなるの?
皆さまご存じの「耐震偽装姉歯事件」のとき,このような問題が実際に生じてしまいました。
そこで,事業者が倒産等しても,賠償を受けることができるようにしたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。
この法律では,建築業者,販売業者に,保険に加入するか,供託するかのいずれかを義務づけています。
対象になるのは,平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅です(住宅ではない建物,例えば,店舗や工場は対象外です)。
大規模なハウスメーカーは,供託していることが多いですが,それ以外のほとんどの建築業者,販売業者は保険に加入しています。
自動車で言えば自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と同じような強制保険と考えればいいでしょう。
以下では,「住宅瑕疵担保履行保険」について説明します。

● 瑕疵担保履行保険について
瑕疵担保責任保険契約の特徴は,次に挙げる4点です。
第1に,建築業者(建売の場合は販売業者,以下同様)が保険料を支払いますので,注文者(建売の場合は買主,以下同様)が支払うことはありません。
第2に,補填される瑕疵の範囲ですが,「構造耐力上主要な部分」と「雨水浸入防止部分」の瑕疵(「特定住宅瑕疵」といいます)です。これは,品確法94条1項,95条1項の特定瑕疵担保責任の範囲と同じです。
第3に,原則として,建築業者が特定瑕疵担保責任を履行した際に当該業者の請求に基づき,住宅瑕疵担保責任保険法人がその履行によって生じた当該業者の負担を填補することになります(注文者からの直接請求は後述)。
第4に,保証される期間は,新築住宅の引渡し時から10年です。保険証券に保険期間が記載されています。保険証券は大変重要な書類ですから,大切に保管しておいてください。
● 注文者からの直接請求について
住宅瑕疵担保履行法は,「建築業者等が相当の期間の経過しても特定住宅瑕疵担保責任を履行しないときに,新築住宅の発注者等の請求に基づき,瑕疵によって生じた損害を補填する」と定めています。これを直接請求といいます。自動車の自賠責でも,被害者が直接請求できるようになっています(自賠責の場合は「被害者請求」といいます)が,それと似た制度です。
瑕疵担保履行保険法では,「相当の期間を経過しても・・・・・・履行しないとき」とされていますから,事業者が倒産した場合に限らず,注文者が複数回に渡って修補等を請求しても履行に応じないとき等でも直接請求は可能です。
● 何が支払われるか
保険から支払われるのは,①.補修に要する費用が中心ですが,その他に,②調査費用,③仮住宅・移転費用も対象になります。その他,保険法人によっては,求償権保全費用や争訟費用が対象になっているものもあります。填補額の限度は,2000万円です。
なお,事業者が瑕疵担保履行保険に請求するときは,損害額の80%が填補されますが,注文者からの直接請求の場合は,100%補填されます。
● 住宅紛争審査会を利用できる
保険付き住宅の場合,「公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センター」が実施している「住宅専門家相談」を受けることや紛争が生じた場合には「住宅紛争審査会」を利用できます。
住宅紛争審査会の申立について,保険付き住宅であれば,対象となる紛争は上記しました「特定住宅瑕疵」に限定されません。「壁紙が切れている」「追加工事代金を請求されている」というような紛争でも申し立てできます。
一方,供託住宅は(建築性能評価を受けた住宅でなければ),住宅専門家相談,住宅紛争審査会は利用できません。
● おわりに
瑕疵担保履行法は,事業者が倒産等した場合においても注文者が少ない負担で瑕疵のついての紛争が解決できる様々な仕組みを設けています。注文者にとってとても頼れる存在です。